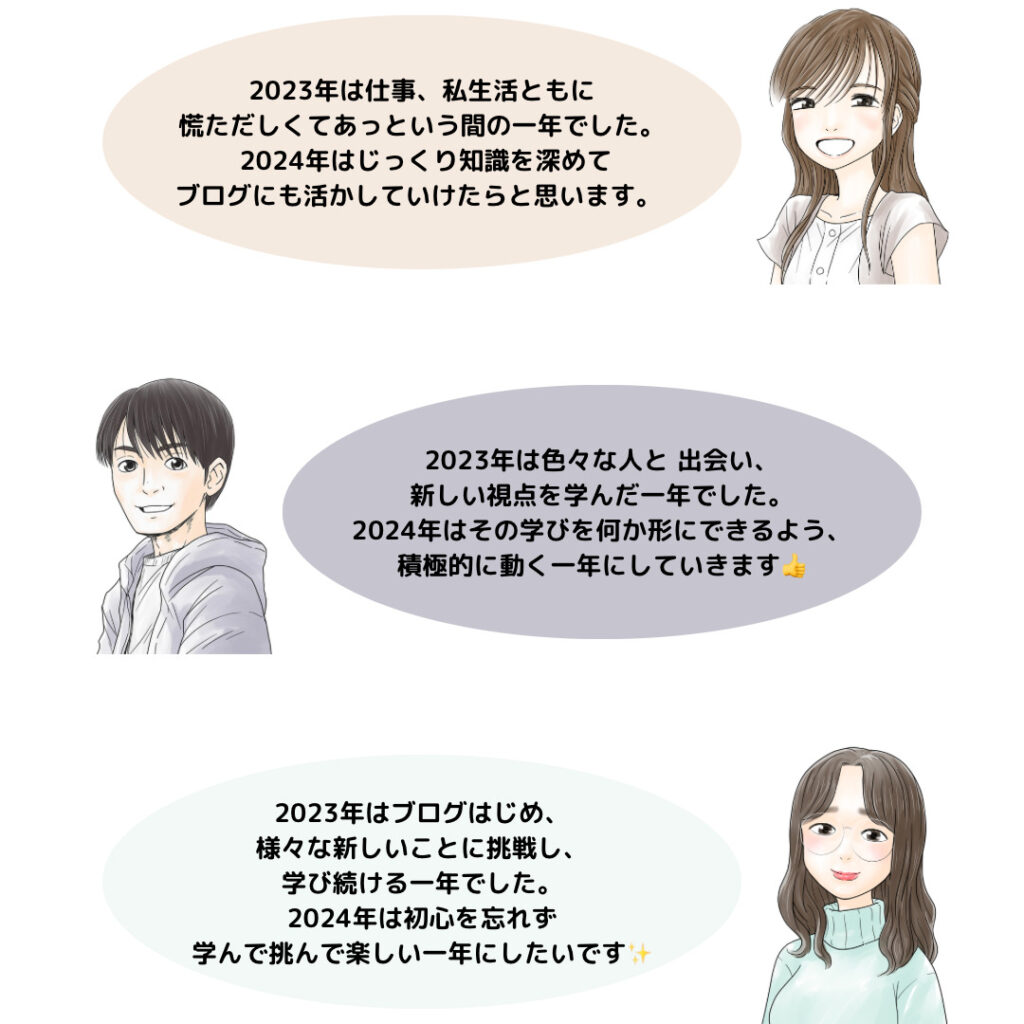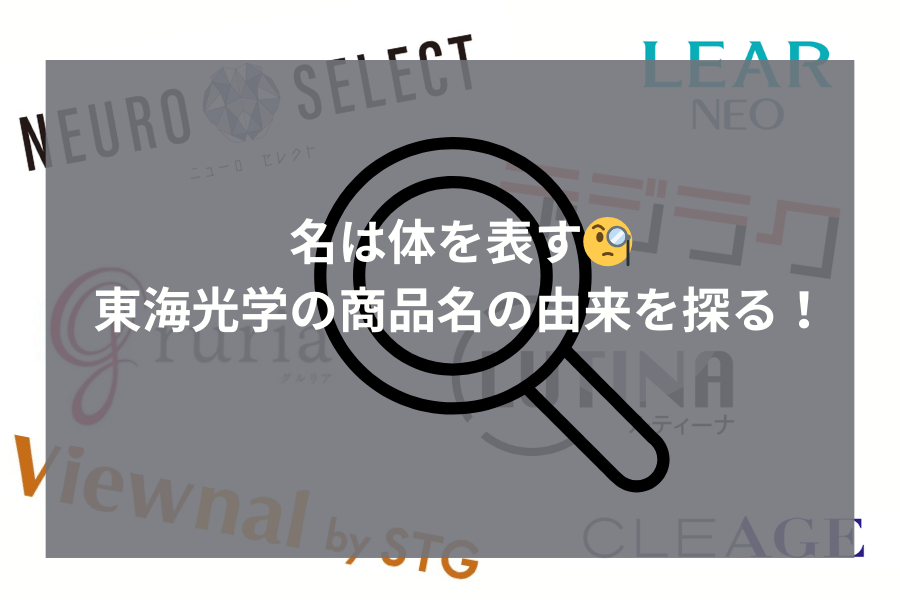こんにちは!201号室のなみです。
私、初めてのブログにも書いていましたが、
2023年は『知的好奇心の赴くままに行動する』という目標を立てていました。
バスケットボールやスノーボードを始めたり、
人生初!の海外旅行に行ったり、公私ともに様々な新しいことにチャレンジできた一年でした💪
さて、新年になり心機一転、メガネを新調する方も多いのではないでしょうか。
皆さんがメガネを作製するときの選ぶ基準、
フレームの形や色、鼻や耳との相性などなど様々あるかと思います。
今回のブログではそんな眼鏡を選ぶ時のひとつのヒントになるような
眼鏡作製技能士という資格をご紹介します!
眼鏡店に携わる方なら耳にしたこともあるかと思いますが、
日常過ごしていて触れることの少ないこの資格について、ご存知ですか?
眼鏡作製技能士は「国家検定資格」なのです。
知識
・視機能、光学、商品、眼鏡販売、
加工作製、フィッティング
・企業倫理、コンプライアンスに関する
【幅広い知識】
・眼鏡業界に関する
【専門的な知識】
能力
・お客様のニーズを汲み取る
【コミュニケーション能力】
・お客様に合った眼鏡を作製する
【測定・加工・フィッティング能力】
・正しい装用・取り扱い方法を説明する
【説明能力】
要するに明確な知識と技術を得た証明になる資格です🎓
そしてなんと、東海光学にも眼鏡作製技能士の資格を取得された方が在籍していたのです。
その方に伺った内容をもとに少しかみ砕いて説明いたします👀👌
眼鏡作製技能士という資格は今年2023年にスタートした資格です。
元々は、認定眼鏡士という資格がありました。
こちらは2001年に民間資格として誕生し、昨年2022年に廃止されました。
眼鏡作製技能士と認定眼鏡士の大きな違いは、
国家資格なのか民間資格なのかという点です。
認定眼鏡士はフィッティングや加工といった眼鏡の販売や修理に関する
知識があることを証明するものでした。

ですが、近年多様化・高度化する眼鏡へのニーズに対し、
適切な診断や治療と適切な眼鏡作製の両方の実現に向けて
眼科医と眼鏡店が連携しつつ眼鏡作製ができるよう誕生したのが
眼鏡作製技能士なのです!
そして資格は取得して終わり!……ではなく、最新の技術や商品知識などを習得するため
繰り返し学び直す『リカレント教育』も行っています。
安心の教育体制ですね😊
レンズメーカーに勤める中で、仕事内容と直接的に結びつかなかった
眼鏡作製技能士という資格。
東海光学で働く方はどのようにして仕事に活かしているのでしょうか?🤔
今回私がお話を伺った方は、元々は認定眼鏡士の資格を取得されていました。
そもそもこの認定眼鏡士の資格取得を目指された理由は、入社して数年が経った頃に
眼鏡レンズを設計するにはレンズだけの知識では足りない、と感じたからだそうです。
東海光学が製作しているレンズは、丸レンズ単体で使用するものではなく
フレームに枠入れされた『眼鏡』として使うもの。
資格を取得するための勉強をしていく中で、そのことをより強く実感されたそうです。
実際に東海光学には、マイチューン・iロケーションリミックス
・中心窩透過光設計などの設計があります。
上記は累進レンズに付随しているオプション設計となります。
専門用語で難しいのですが、簡単に説明いたします🤔💭
マイチューン
—フレームの玉型形状(大きさや縦の長さ)とアイポイント(黒目の位置)のデータから
歪みやボケを抑えて、見えやすい掛け心地を実現する設計。
iロケーションリミックス
—ひとりひとり異なる、そり角・前傾角・頂点間距離を測定することで
眼とレンズの立体的な位置関係をレンズ設計に反映させる設計。
中心窩透過光設計(ちゅうしんかとうかこうせっけい)
—視力が最も高くなる中心窩を考慮した、透過光最適設計。
マイチューンにはフレームの形状、iロケーションリミックスには眼鏡の装用状態、
中心窩透過光設計には眼光学の知識、というように資格取得時に学んだ様々なことが
実際の設計技術として活用されているようです👓
最後に、
今後も継続的に勉強し、開発者同士で知識を共有し、新しい商品開発をしていきたい
と仰っていました!
これから誕生する設計やレンズにも要注目です✨
また、一般社団法人 日本メガネ協会が運営している「かけごこち」というHPでは
眼鏡作製技能士の資格を持つ方の名簿を見ることができます👀
眼鏡の新調を行うのにうってつけの年始🌄
多くの選択肢があり迷われる方へ、お店探し際のひとつのヒントになれば幸いです☺